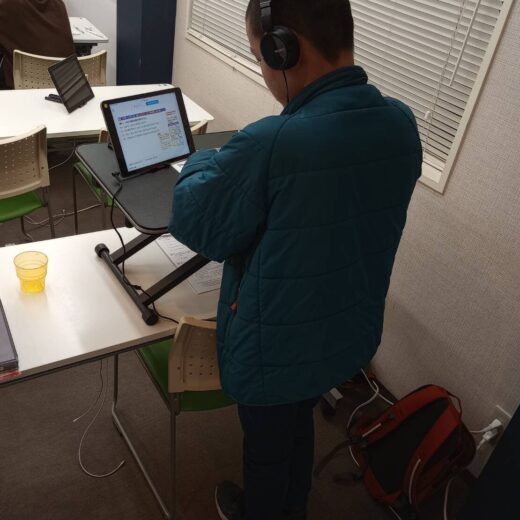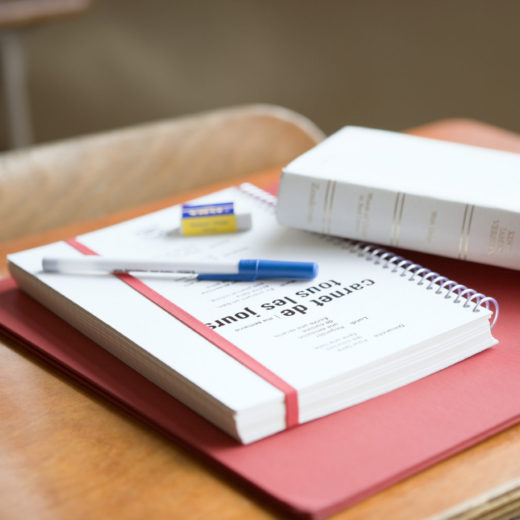テスト期間です。
テスト期間も学びホーダイなので素晴らしい出席率で連日みんな頑張ってくれてます。
テスト期間は学習システム以外の内容で、学校のテスト範囲表にあるワークやプリント類を進めることもOKにしています。
基本的には自習に近い形になりますが、勉強のしかたや質問対応などで私も口をはさみますw
これはテスト勉強のしかたそのものを改善する必要のある子がとてもたくさん多いからです。
そんなエピソードのひとつ。
六中の2年生の子たちがせっせと取り組んでいたのが「歴史の漢字プリント」なるもの。
六中の定期テストでは漢字で答えないと〇にしてもらえないから学校の先生が作ってくれているんでしょうね。
それに取り組むのはいいんですが、子どもたちはそのプリント1枚を机に出して必死で漢字を書いていくんです。
(今回だったら「大航海時代」とか「南蛮貿易」とか「天正遣欧使節」とかです)
・・・ここで違和感を感じた方はステキです(笑)
やってる子に「『天正遣欧使節』って何?」と質問すると「知らない」と答えてくれました。
もう分かりましたか!?
彼らは言葉の意味も知らずにただそこに書かれている漢字を書き写す作業をしています。
強めに言うと、これは「作業」であって「勉強」ではありません。
これは国語や理科などで漢字を練習するときも同じです。
漢字の意味や中身を知らずにひたすら書いていても頭には入りません。意味も漢字の形も。
逆に漢字の一つ一つの意味が分かってくると、漢字から熟語などの意味が想像できるようになります。
例えば歴史で時々出てくる「勅」の字は「天皇」の行動、言葉にしか使わない言葉です。
これが入っている用語は「天皇」に関係している、ということになりますね。
ですので生徒には以下のように指示しました。
「提出期限は…テストの日まででいいんやね?じゃあ、最初にそれをやらずに社会の勉強を進めながら、そのプリントの漢字が出てきたらそのときに練習していこう。提出期限が迫ってきたら、まだ書いてない用語を練習して提出しよう。その用語を勉強してなかったらそのときに勉強してしまおう!」
こんな感じです♪
社会は覚えることがとっても多い教科です。
いかに無駄なことをせず効率よく学習を進めるかが得点アップのカギとなります。
勉強のしかたを変えずに「テストにこれが出る」だけ教えても何の解決にもならないのだと思っています。